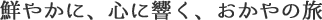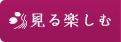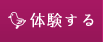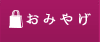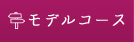あじさいの最新情報は岡谷市観光協会FaceBookでも発信中!
フォトギャラリーもチェックしてね!
7/23
小坂観音院境内(小坂公園)で4年ぶりに本祭りが行われました。
チアダンスチームのダンスや大正琴など多彩な催し物があり、いつもは厳かな雰囲気の境内がとても賑やかでした✨
振舞いの「由布姫ぜんざい」は土手かぼちゃが入っており、小坂区ならではのぜんざいだそうです!あじさいは全体的には終わりですが、木陰に咲いているあじさいは綺麗に咲いていますよ。






7/19
連日の猛暑日、あじさい達も疲れてきている様子。
枯れている部分も目立つようになり花期も終わりの様です。




7/11
園内全体に花が付き、梅雨時期を鮮やかに彩っています。
とはいえ、花付きが悪い株も見受けられます。(去年よりは開花状況格段と良いですけどね!)




7月4日
青い空、ブルーのあじさい、そして諏訪湖。高台から素敵な景色が広がっています。
先週より開花が進み綺麗に咲いていますよ(^^)/






小坂観音院正門からは樹齢500~700年ともいわれるサワラ並木があり、静寂な空気に身が包まれます。




6月26日
昨日(6/25)より「あじさい祭り」始まりました。提灯も飾られています。
現在、園内1/4くらいの開花状況です。今年は去年より花の付きは良いそうなので満開になるのが楽しみですね(^^♪




咲き始め 6月21日
徐々に咲き始めています。諏訪湖を望む高台が彩り鮮やかに飾られるのはいつ頃になるでしょう。




つぼみ 6月14日
梅雨入りし嫌な時期ではありますが雨に映えるあじさいシーズンです。小坂公園のあじさいも
つぼみが増えてきました。中には色づいてきているものも!
由布姫あじさい祭り 6/25(日)~7/23(日)
岡谷市湊の小坂観音は武田信玄側室、由布姫(湖衣姫)が治療していた場所として伝えられており その供養塔があります。 また、万病を癒す賓頭盧尊者座像(びんずるそんじゃざぞう) 樹齢千四百年と言われるビャクシンの大木、樹齢四百~七百年のサワラ並木があり 木々のなかの凛とした空気が気持ちよく、なんだか心が落ち着きます。 そのすぐとなり小坂公園では毎年7月ごろ八百株ものアジサイが咲き誇ります。 諏訪湖を望む高台で彩り鮮やかなアジサイをぜひご覧ください。
【祭り期間中の臨時駐車】
普通車:小坂公民館横 (公園入口 階段まで徒歩6分)
大型バスの駐車場、進入経路は事前にお問い合わせください。
なお、バス乗降場所は味澤製絲㈱様のスペースをご利用いただけます。※長時間の駐車はご遠慮ください。(公園入口 階段まで徒歩3分)
【お問い合わせ】
岡谷市商業観光課 TEL 0266-23-4811
岡谷市観光協会 TEL 0266-23-4854
小坂公民館(午前中のみ) TEL 0266-23-9730